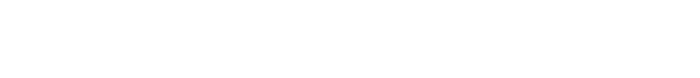男鹿水族館GAOでは、飼育する生きものが心身ともに健康な生活が送れるよう、以下の通り指針を定めています。
男鹿水族館におけるアニマルウェルフェアに関する指針
1.はじめに
本指針は、飼育する生きものが心身ともに健康な生活が送れるように定めるものである。
アニマルウェルフェア(以下、AWとする。)には複数の定義があるが、ここでは「飼育および展示における個々の身体的・心理的状態等」と定義する。 (JAZA 動物福祉基準 第1条)
多くの動物園・水族館は、動物を調査研究し、飼育・展示を通して種の保全に貢献するとともに、様々な教育活動を行って人と野生動物が共生できる社会の実現を目指している。
当館も、生きものを展示などに利用するうえで、その生きものの身体・行動特性、各動物との相違点を理解し、その本来の性質を十分に発揮できるような環境を中長期的な計画性をもって提供し続けることを飼育活動の原則とする。
また、来館者に対しても生きものに対する敬意を育み、レクリエーション機能の重要性を踏まえながら生物多様性、環境保全、SDGsなどの理解を深める教育活動を行い、多くの人に利用してもらう事が男鹿水族館GAOにおけるAW向上に繋がるように行動する。
2.AW向上に向けた行動規則
5つの自由(①飢えと渇きからの解放 ②不快からの解放 ③痛み、怪我、病気からの解放 ④正常行動発現の自由 ⑤恐怖・苦悩からの解放)および、5つの領域(栄養、環境、健康、行動、精神)などを参考にしながら活動を行う。
1)科学的な知見に基づいた飼育の実践
生きものが24時間を通して充実したものとなるように努力する。
個人的な見解に偏らずに、図鑑、専門書、論文などによる知見も取り入れ、限られた空間の中で実現可能なことは積極的に取り入れ、将来的に問題となり得る事(飼育密度、成長後の大きさなど)は予め避ける。
2)生きものの生態に根差した飼育環境の確保
生きものの運動能力、生態などを考慮し、限りある空間の中で最大限本来の行動パターンが発現できるように努める。
また、生きものが望めば来館者、他の個体から適切に距離を保ち、隠れることができるなど行動の選択肢が常に複数保たれるようにする。
水草、海藻などの導入についても積極的に取り組む。
3)環境エンリッチメント(※)の実践
環境エンリッチメントは、安全で生きものにとって良い刺激となるもので、本来の行動を引き出すものとし常に行うことができるように努める。
また、ライフステージや、飼育環境により適切な内容が変化することに付いては考慮し、新規性の高いエンリッチメントを行う場合は安全性に十分留意し観察などを徹底しリスクに対する評価を適切に行う。
※ 環境エンリッチメントとは、
生きものが心身ともに健康で暮らせるように生物学的な知見やライフヒストリーをもとにした工夫を行うこと。
(近年では物理的、社会的、採食、感覚、認知の5つに主に分類される)
4)ハズバンダリートレーニングの実践
ハズバンダリートレーニングは,治療や採血など生きものにとってストレスになり得る場面に積極的に慣らすことで、人と生きもの双方の負担を軽減するための訓練となるため積極的に取り入れるように努める。
また、ハズバンダリートレーニングの実践については、その目的、計画と進捗についての共有を確実に行い関係する人が同じ意識で取り組めるようにする。
5)客観的な評価の実践
AWに関する評価は、人間(担当者)の志向、感情ではなく、生きものの視点に立つことが重要である。
評価を実践する際は、チェックシートなどを用いて状況、個体、種など様々な要因に左右される事情を踏まえ個別事例毎に評価が行えるように努める。
評価は、頻度、段階を定めて行えるような制度設計として、特に対策が必要と判断された場合はその対策についての検討、改善計画についての立案まで行う。
6)質の高い健康管理、獣医療の実践
獣医師、飼育担当者らが協力し、生きものが健康に暮らせるような予防を目的とした血液検査などの医学的措置についても幅広く行うように努める。
与える飼料についても、獣医師、飼育担当者で(体重増減、繁殖前の対処などの)意図を共有しながら適切な内容になるように配慮する。
また、体調不良など通常とは違う対応を求められる際は、連絡を密に行い適切な対応が行えるように特に注意する。
安楽殺は苦痛を感じている傾向がみられ、中長期的にも開放される見込みがない場合、または最低限の生活の質が保てないと判断される場合には選択する。
安楽殺の判断にあたっては、安楽殺のガイドラインを定めそれに従う。
以上
男鹿水族館における安楽死に関する指針
1.はじめに
本指針は、飼育する生きものについてやむを得ず殺処分する際に、安楽死を行うため必要な手順、手続き、手法などを定めるものである。
安楽死は、一般的に痛みや苦しみを最小限、または排除して、個々の生物の命を終わらせることを意味する(米国獣医学会 動物の安楽死指針2020年度版)。
WAZA動物福祉戦略(2015)によると、動物は生涯を通して敬意を持って扱われるべきであり、必要な場合には人道的な死を与えられるべきであるとされている。
また、すべての動物園・水族館は、動物の安楽死の取り扱いに明確な指針を持たなければならず、安楽死をいつ、どのように実施するのかが明確に述べられていなければならないとされている。
よって、(1)生物を飼育する施設は、生物の利益・利害を踏まえて、あるいは福祉の問題として、生物を死に至らしめる人道的な配慮をすること、(2)可能な限り最も迅速に、かつ最も痛みや苦しみのない死を誘導するための人道的な技術を知り使用する責任がある。
飼育する生きものの生命の尊厳に配慮しながら、男鹿水族館GAOで持続的に適切な運用が行われるように努める。
2.安楽死が想定される状況について
動物の健康状態が著しく悪化し、
・怪我や病気など動物の健康状態について、獣医学的な診断が非常に悪く、中長期的に動物福祉の低下が予想される
・治療が不可能
・高齢の動物が加齢により著しく健康機能が低下
3.安楽死の実施ついて
1)安楽死は、社内で定めた判断基準「生活の質(QOL)評価シート」に基づいて実施する。判断は画一的な基準に基づいて行い、安楽死不適用となった場合についても同等程度の状態が継続する可能性には十分留意する
2)安楽死に用いる手段、手法は社内で定めたものに限る
4.広報について
安楽死についての周知は、教育的観点から重要であるとの考えに基づき広報活動を行う事とするが、すべての事例を公表する必要はないものとする。
但し事実については隠さないように徹底し、且つ予想される意見により必要な処置を見送る事は避け、あくまで動物の状態でのみ判断するように努める。
以上